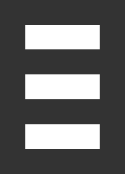目[mé]の作品の中でも、制作者の思考のシグネチャー的な部分がよく表れている作品である。空中に吊り下げられた8000個の時計のムーヴメントは、一見すると鳥や、魚が形成する群れのようにも見える。
̶
ムーヴメントを仮想的な生物種の個体、全体を群とみれば、個―群の関係がにわかにリアリティを持ってこの作品の中に浮かび上がってくる。個の意思に群の形成を企図する要素がなくとも、全体は、個の意思とは無関係の、一つの巨大な生命体であるかのごとく振舞う(ように見える)。
̶
そのように見ることで本作は、我々の存在の不確実性の核心に迫る、鋭い問題提起としての機能を帯びてくる。個々のムーヴメントの刻む時間がそれぞれの主観的な時刻や自由意志のメタファであるなら、全体の見せるクラウド的なヴィジョンは一体何を意味するのか。制作者は多くを語らず、問いのプロセスのほとんどを鑑賞者に大胆に委ねてしまうという作風も、彼らの特徴といえよう。
̶
個が生存適応的に振舞った結果生じる単純な集合が群なのか、群を形成/維持するための一部分が個であるのか。これを両極とする直線の上を、鑑賞者の視点は行き来する。全体を見渡せばチラチラと動く夥しい数の秒針が目に入り、一つに着目すれば詩的ですらあるムーヴメントの、死に向かって容赦なく時を刻む着実な律動が目に映る。
̶
我々が形成する群自体もまた、同じ直線の上に在り、平衡点は常に移動していて動的に振る舞う。個を選ぶ視点は、ごく短い期間、一定の魅力を放って群衆に受け入れられることもあるが、多くの場合はエゴセントリックと判断され、醜い、あるいは汚いと評価されて排除されてきた。群を重んじる視点は、美であり利他であり善であると時には政治的な意図に裏打ちされ過度に称賛もされるが、程度の差こそあれ個の犠牲を強いる。どちらに傾くのかは環境依存的であり、どちらが良いも悪いもなく、ただ動的であり不確実性を内包する存在であることそのものが種として選択した生存戦略であるということになろう。
̶
我々の生来の性質が善であるか悪であるかを査定する者は我々以外のどこにも存在せず、この問題を論じる行為は再帰的であり論争を楽しむ知のトレーニングまたはそれによるコミュニケーションを促進する以上の意味はない。が、その判断を脳機能の一部が生得的に担っているため、あたかもこれが天与の基準であるかのように我々は認知されられており、人間の存在を悪である、善である、醜い、美しい、などと主観と客観が綯交ぜになった状態で評価を下さざるを得ない。そこに我々の弱点があり、面白みもある。こうした形で、本作は美の意義や価値そのものを問いなおす契機を鑑賞者に与えるものともなっている。
̶
中野信子
脳科学者/東日本国際大学教授
*MonET公式カタログ(p29)より転載